確かな技能・技術の養成にあたって◆この人のことば◆
- 北海道立札幌高等技術専門学院長 櫛谷 昌俊
約30年その大部分を北海道の職業能力開発に携わり、一昨年から20年ぶりの現場(高等技術専門学院)に勤務してみて、今さらながら、職業訓練が飛躍的に高度化・複合化そしてまた多様化し、大きな成果をあげていることを実感している。
しかし、その中にあって、新規学卒者の養成訓練について、日頃危倶していることもある。
それは、施設設備も近代化され、指導員のレベルも数段アップしているけれど、一方、地域や企業との結びつきやサービス度はそれなりにアップしてきているのだろうか、また学生への職業能力開発のあり方もこれでよいのだろうか、ということである。
ちなみに、よく業界懇談全等で企業側から“即戦力になる人材がほしい"と言われる。
そこで私どもは、地域や企業二一ズに合った訓練内容にすべくカリキュラムを見直し、内容も多岐にわたって充実を図り必要な機械整備も行ってきたが、さてそこで、訓練を受けた学生のその仕上がりはどうだろうか、求められる訓練到達目標に達しているだろうかと考えるとき、ややもすると、指導員の教えたいと思うことが、あるいは学生のやらねばならぬことがあまりにも盛りだくさんで、総花的になり、最も大事ないくつかの事柄の焦点が、ぽけてきてはいやしないかと感じるのである。
即戦力の中には、もちろん確かな技能・技術の習得が大きな要素ではある。しかし、年間1400時間の標準訓練時間で、1年や2年間の訓練期間で修了する学生に対して、あれもこれもとつめ込むのは、消化不良になりはしないだろうか。
限られた時間、設備、指導員体制のなかでは、訓練を受ける学生の個性を生かしつつ、基本を着実に、学生が自ら進んで自立の可能性を確立することができるような訓練の徹底を図ることこそが肝要と考えるし、そのことが、将来的には企業の求めるものにつながると思うのである。
企業が学院に対して求めるものは、これからの社会人・職業人としての資質、つまりその段階段階で与えられる仕事を確実に成し遂げ、常に探求心と向上心旺盛で、職業生活の種々な場面における適応力を、どれだけ訓練しているのかという基本的なことであろうと思う。そして、即戦力とは、当面もっている技能・技術もさることながら、時間に対する認識の仕方であったり、仕事への取り組み方であったり、そしてまた、協調性やめげずにがんばるというようなあたり前のことができる、企業にとってあてになる人間ということでもあると考えるのである。
これから新しく産業の担い手となる若者に対しては、今何ができるかということよりも、これから職業人として長い社会生活を的確に対応していける技能・技術者の育成に心がけることが重要と思う。
先端機器の操作や目先の成果ばかりに視点をおくと、肝心なことがおろそかになりがちになることが懸念されるのである。
そんなわけで、経済効率優先、商業主義優先の最近の風潮の中にあって、確かな技能・技術へのこだわりをもって仕事のできる、そしてそれらのことに対して喜びや生きがいを見いだすことができる人材の養成へ向けて、一層の職業能力開発に心がけ、地域や企業の二一ズに応えていきたいと思うこの頃である。
くしたに まさとし
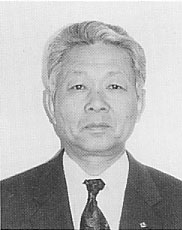
略歴
昭44 北海道労働部職業訓練課勤務
公共訓練係長,管理係長,課長補佐を経て
平元 根室支庁経済部長
平4 商工労働観光部職業能力開発係長
平7 現職
